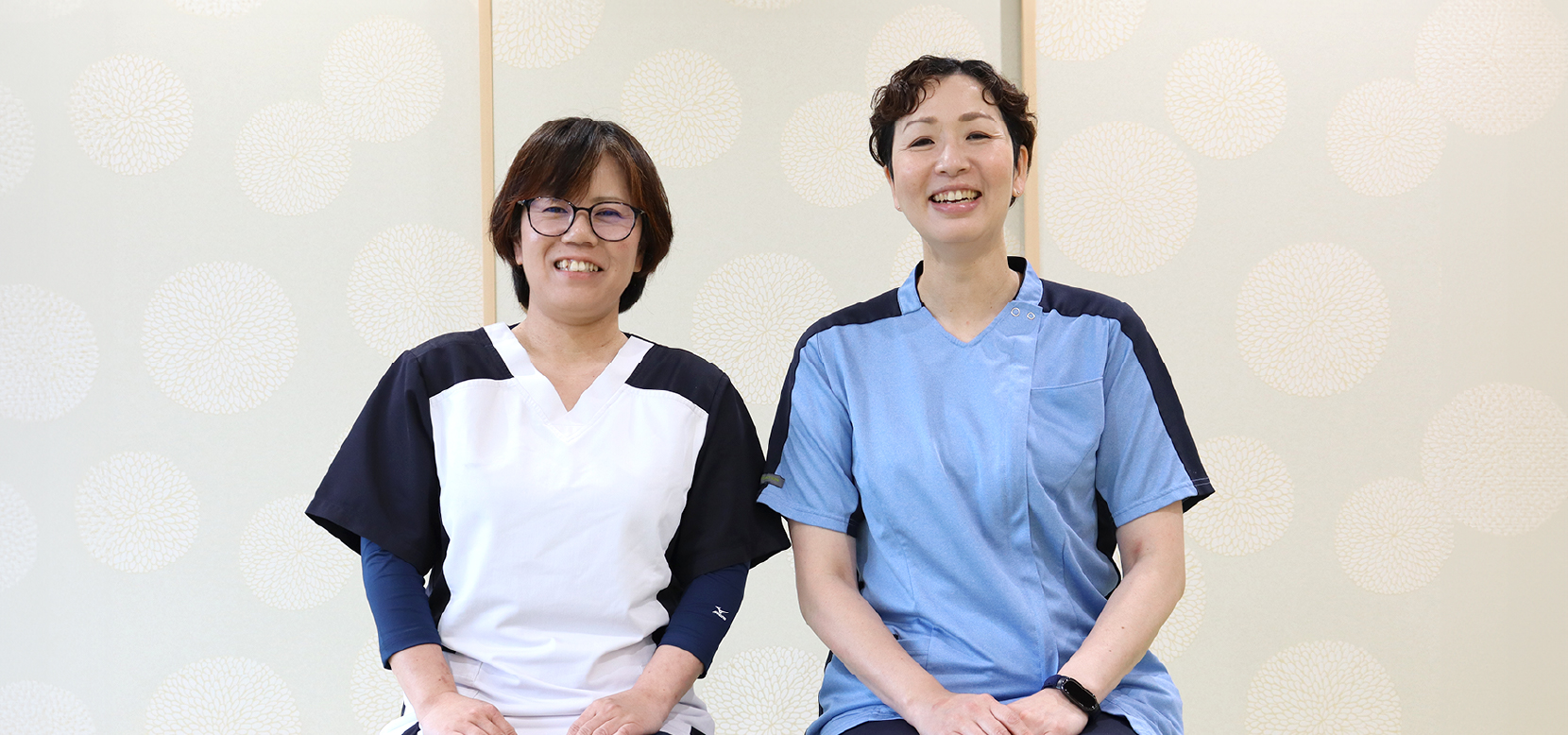
介護医療院 トワイエ尼崎
看護師長
坂本 奈津子
高校卒業後に専門学校へ進学した後、まずは京都のホテルで2年間勤務しました。ところが、当時勤務していたホテルの経営が難しくなり、やむを得ず転職を考えることに。ちょうどその頃、近所の病院から「看護師を目指してみないか」と声をかけられたのが、医療の道に進むきっかけです。
もともと人と関わることや、人の役に立つ仕事が好きで病院で働きながら看護学校に通い、看護師免許を取得しました。
その後は大阪の急性期病院で経験を積みました。こちらも経営が不安定だったため、「もっと安定した、しっかりとした医療現場で働きたい」と考え、尼崎中央病院と出会います。以来、すでに16年にわたり勤務を続けており、これまでに、外科病棟、循環器病棟、地域包括ケア病棟、療養病棟といった幅広い現場を経験してきました。現在は介護医療院で豊富な経験と、患者さんへの温かなまなざしを持つ、頼れる看護師として活躍中。
介護医療院 トワイエ尼崎
言語聴覚士
桑山 晶子
大学卒業後、国民健康保険団体連合会の歯科部門でレセプト審査などの業務に携わっていました。3年ほど勤務の後、家族の事情で退職を決意。長年病と向き合っていた母親を看取った経験が大きな転機となりました。
その後、母の療養中に支えとなった言語聴覚士の存在を思い出し、自らもその道を志しました。
資格取得後は、大分県のリハビリ専門病院で4年間、基礎からしっかりと臨床経験を積み、神戸に戻ってからは、回復期リハ病棟の立ち上げに関わり、7年間勤務。出産・子育てを経て訪問リハビリなど在宅分野にも携わり、幅広い医療現場で活躍してきました。
そして、子育てと両立しやすい環境を求め、中央会のスタッフの一員として介護医療院の立ち上げから参加。確かな技術と利用者さん一人ひとりに丁寧に向き合い続けています。

介護医療院トワイエ尼崎の特徴
-
坂本
介護医療院は、24時間体制で看護師や医師が常駐している施設です。医療的な処置が継続的に必要な方にとって、安心して暮らせる“生活の場”として選んでいただける場所なのではないかと感じています。
-
桑山
そうですね。生活の場でありながらしっかりと医療的な関わりが継続できていると思います。その中で、リハビリに関しても一人一人に向き合う時間を多く取る事ができています。そういった点は他施設との差別化を実現できていると感じます。
-
坂本
医療的な要素がしっかりとしていてこその「安心して暮らせる“生活の場”」だと思います。そのために職種を超えた繋がりを大事にしながらチームで利用者様を支えているという形です。
また、家族様との距離が近いことも一つの特徴だと思います。
毎日面会にくる家族様もおられ、顔見知りになって本当に気軽に話せる関係になっております。 -
桑山
リハビリの時も「今日もありがとう。」「またよろしくねー。」と言われたり、本当に家族様と一緒になって診ているという感じです。チームで支える、ということを大事にしていますが、家族様も含めてチームになれていると思います。

看護・リハビリのそれぞれの役割
-
坂本
看護の役割は、介護と協力を図りながら、安全をしっかりと担保するということが非常に大事ですが、先ほども言った通り、チームで動かなければなかなか難しいです。より利用者様の生活部分を多く見てくれているのは、介護スタッフなので、その情報をしっかりと共有してもらうことが非常に重要です。
-
桑山
その部分はリハビリにとっても全く同じですね。リハビリだけではわからないところを看護・介護から情報をもらい、また反対にリハビリでの状況やその時々の様子をフィードバックする。この循環が非常に大事だと思います。それぞれの専門家がそれぞれ意見を交わすことでより良いものが提供できるのだと思います。
-
坂本
リハビリスタッフは本当にしっかりとフィードバックしてくれるので非常に助かっているし、看護と介護とはまた違うところをサポートしてくれていると感じます。
-
桑山
表現が正しいかどうか分かりませんが、看護と介護の「間」であり、「先」だと考えていて、現状を把握しながら適切に対応するのと同時に、可能性部分にしっかりと焦点を当て、適切に実行していくことの両視点が必要だと思っております。

看護×リハビリ現在と可能性
-
桑山
利用者様が落ち着いた生活の中でも様々な感情(喜び、楽しみなど)を感じてもらえればと思うので、リハビリの中で少しでも一人一人の欲求をしっかりと捉えていきたいのですが、その表現が難しい利用者様も多いので非常に悩ましいところです。
-
坂本
その通りですね。どうしても表現が難しい方もおられますし、同じ方でもその時々で機嫌や調子も大きく変わります。やはりその点も一つの職種で何かをしようとするのは限界があるので、情報や意見を共有し、チームで動くことだと思います。リハビリの時に「こういった反応があったよ」と聞き、「そんなことができたの?!」とびっくりすることもあります。
-
桑山
少しずつできることを増やそうとしたり、また反応を引き出せるようにしたり関わりを工夫し続けることで変化が生まれます。その変化を逃さず捉え共有する、といったことを継続することで、さらに少しずつ変化が生まれる、ということだと思います。
-
坂本
更にそれを看護と介護がしっかりと継続することが重要だと思います。その小さいかもしれないけれど、良き驚きが多く生まれ、連続することで、利用者様も私たちスタッフも喜びと楽しみを感じることができるのだと考えております。
「看護×リハビリ」は介護医療院にとって可能性の塊だと思います。



